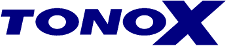コロナ禍で需要が右肩上がりの特装車、キャンピングカー | 特殊車両ならトノックス
1.キャンピングカーとは
キャンピングカーは車内で主に寝泊まりする設備を備えた自動車です。つまり、キャンプ用の設備をもった自動車のことで、別名「キャンパー」とも呼ばれます。
自動車の中で寝泊まりや料理、洗面などもできる設備があるキャンピングカーには、設備すべてを自動車に装備した「自走式」と、トレーラーに装備した「けん引式」があります。
「自走式」の主なものには、
フルコンバージョン(通称フルコン)
シャシーからキャビンのすべてを架装メーカーが製造したタイプ。
キャブコンバージョン(キャブコン)
ピックアップトラックやワンボックスタイプの自動車をベースにしてキャビンを架装メーカーが製造したタイプで、エンジンルームの上にキャブ(運転席部分)があるキャブオーバー車をベースにしたキャンピングカーを指します。運転席より後ろが専用のシェルで作られており、人が立って歩けるほど広いのが特徴で、多くのモデルは運転席上部にまでせり出したバンクベッドを持ち、キャンピングカーらしい見た目をしています。
バンコンバージョン(バンコン)
バンやワゴン等をベースにし、キッチン、サニタリー、就寝スペースなど車内架裝に重点を置き、主に商用バンをベースにしたキャンピングカーです。基本的にはバンの中のみを架装するため、外見の変化は少なく、パッと見ではキャンピングカーかどうか分かりにくいタイプです。
軽キャンピングカー(軽キャンパー)
軽自動車の貨物車や乗用車をベースにした、コンパクトなタイプ。
などがあります。
日本では専用の自動車として販売されている車両がごく限られているため、ベースとなる自動車を購入して架装する必要があります。就寝設備がある、水道設備や炊事設備がある、など『用途区分通達(国土交通省)』に基づき架装した場合、ナンバープレートに表示される「自動車の種別及び用途による分類番号」は「特種用途自動車」を表す「8」となります。
2.キャンピングカー人気のヒミツ
キャンピングカーは、車内で寝泊まりができるうえ、サニタリーの設備があったり電力が使用できたりと、快適なキャンプ生活を送れることが人気の要因のひとつと考えられます。オートキャンプ場や専用のRVパークなど車中泊ができる場所も全国にあり、プライベート空間を確保しながら、オリジナルにカスタマイズしたキャンプを楽しむことができます。
実際、オートキャンプ場やRVパークなどで、バーベキューやピクニックなどのアウトドアライフを楽しむ用途や、比較的短期の旅に利用出され、交通機関などの出発時間やウィルスの感染などを気にせず、自由気ままに利用できるのも魅力のひとつです。
 コロナ禍で需要が右肩上がりの特装車、キャンピングカー
コロナ禍で需要が右肩上がりの特装車、キャンピングカー3.高まり続けるキャンピングカーの需要
日本RV協会「オートキャンプ白書2022」によると、オートキャンプ参加人口(推定値)は、2012年の720万人から年々右肩上がりに増加し、2019年には860万人となりました。2020年は、新型コロナウイルスの感染拡大により人口が大幅に減少しましたが、2021年は増加に転じて750万人まで回復しています。
また、オートキャンプ場稼働率の推移も、参加人口の推移に比例して上昇し、2021年に過去最高を記録しています。
キャンピングカーの保有台数については、2005年の50,000台から増加を続けており、2021年には約2.7倍の136,000台を記録しました。また、ここ2年は1年あたり8,000台を上回るペースで増えています。もちろん、キャンピングカー販売台数も増加傾向で、特に2011年と比べ、水回りなどの設備が整った「8」ナンバーのキャンピングカーが約3倍と顕著に増加しています。
4.キャンピングカーの需要が増加した背景
第一次キャンプブームは、1990年代のことです。移動手段だった自動車が趣味やレジャー目的としても発展してきたのがこの時期です。1996年に最多の約1580万人を記録しました。やがて、第一次キャンプブームは収束しますが、2010年頃から第二次キャンプブームが始まりました。
オートキャンプ場の平均稼働率は2011年に底をつき、その後、増加に反転しています。
第二次キャンプブームが第一次と大きく異なる点は、ファミリー中心の第一次に対し、ソロキャンパーが増えていることです。日本オートキャンプ協会による調査では、2021年の傾向として「ソロキャンパー」が増えたと63.8%のキャンプ場が回答しています。
このように、近年の急速なキャンピングカーブームの土壌には、第二次キャンプブームがあります。
さらに、新型コロナウイルス感染拡大が、ブームに拍車をかけ、公共交通機関や宿泊施設での三密回避を狙い、キャンピングカーを利用する傾向が高まったそうです。
日本オートキャンプ協会による調査では、利用者が増えたキャンピング場のうち78.2%が、「コロナ禍による影響(三密回避など)」を理由に挙げています。